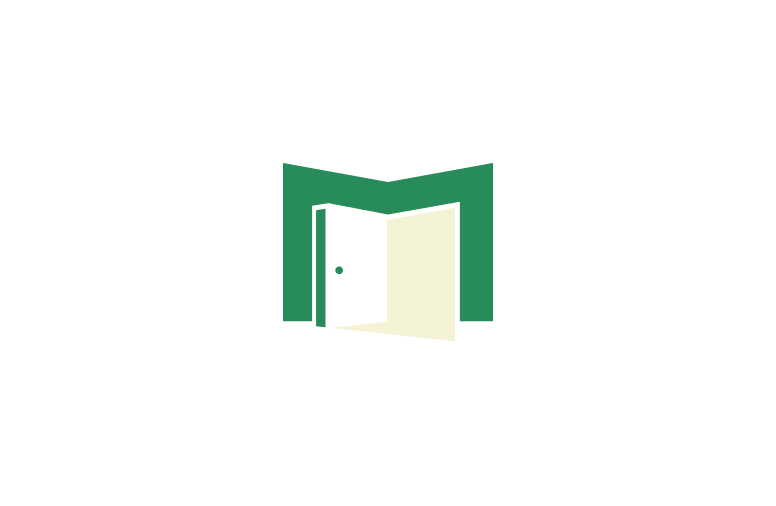皆様こんにちは!㈱MIJの桑原です。
今回は「マンションにおける防災対策」について、分かりやすくまとめました。
日本は地震や台風など自然災害の多い国です。マンションでは多くの世帯が共同で暮らしているため、災害時には個々の家庭だけでなく、住民全体で連携し、安全を確保することが求められます。
本稿では、マンション防災の重要性と具体的な取り組みについて、ポイントごとにご紹介します
近年、地震や台風、大雨といった自然災害が頻発しています。特に都市部においては、密集する建物や人口密度の高さから、災害時に多くの混乱が生じやすく、マンションという集合住宅の形態では、その対応がさらに複雑になります。しかし、こうした困難を前にしても「防災は管理の延長線」であるという視点を持てば、私たちができることはたくさんあります。
本記事では、マンションにおける防災の考え方から、実際に必要な備え、そして管理組合としてどのように取り組めばよいのかを、分かりやすくご紹介していきます。
なぜ「防災は管理の延長線」なのか?
防災というと、多くの方がまず思い浮かべるのは「非常食の備蓄」「避難訓練」「家具の固定」など、家庭内での対策でしょう。しかし、マンションに住んでいる私たちにとって、防災はもっと広い意味を持っています。共用部分の安全性、住民同士の連携、災害時の役割分担、復旧体制……こうした要素すべてが、防災の一環なのです。
そして、それらはすでに日常的に行っている「マンション管理」と深く結びついています。たとえば、日常的な建物点検は、非常時の被害を最小限に抑えるための重要な予防措置です。防災倉庫の整備は資産管理の一部ですし、掲示板や回覧板を使った情報共有の仕組みは、災害時においても極めて重要な「情報インフラ」となります。
つまり、「防災」とは特別な取り組みではなく、「管理の延長線上にあるもの」なのです。
災害時、マンションで何が起こるか?
災害が起きた際、マンションでは以下のような事態が発生します。
-
停電・断水・ガス停止
ライフラインが途絶え、日常生活が大きく制限されます。特にタワーマンションなどでは、エレベーターが止まることで高層階の住民は外出も困難になります。 -
通信手段の途絶
インターネットや携帯電話がつながらなくなると、外部との連絡が取れず、孤立するリスクが高まります。 -
住民間の混乱
安否確認や情報共有の手段がなければ、不安が連鎖し、パニックやトラブルの原因になります。 -
共用部分の被害
外壁の崩落、配管の破損、非常階段の不具合などが生じた場合、全体の安全性や避難行動に支障を来します。
こうした事態に備えるためには、「日常の延長」としての備えが不可欠です。
防災の基本は「自助」+「共助」
災害時、最も重要なのは「自助」と「共助」です。行政や消防などの「公助」は、初動では届かないことが多く、まずは住民自身による対応が求められます。
自助:各家庭での備え
-
飲料水・非常食の3〜7日分の備蓄
-
懐中電灯・モバイルバッテリー・携帯ラジオなどの非常用アイテム
-
家具の転倒防止・ガラスの飛散防止
-
家族間での安否確認方法の事前共有
共助:管理組合や住民同士での備え
-
防災倉庫の設置と内容の見直し
-
災害時対応マニュアルの整備
-
防災委員会の設置と定期的な会合
-
年1回以上の防災訓練の実施
-
住民間の連絡網の整備
「自助」だけでも「共助」だけでも十分ではなく、両者が噛み合ってこそ、実効性のある防災体制が構築されます。
実際にあった、管理の工夫が生きた事例
ある関東のマンションでは、数年前の大型台風の際に停電と断水が発生しました。このマンションでは事前に管理組合が発電機と給水タンクを共用部に備蓄しており、停電時にはエレベーター前の照明を確保し、断水時には中庭に給水ステーションを設けて住民に水を供給しました。
また、別のマンションでは、掲示板とは別に「災害時用掲示板」をエントランスに常設しており、災害発生直後から安否確認の一覧表や注意喚起情報が即座に掲示され、住民が自然と集合して協力し合ったといいます。
いずれも「管理の一部として事前に整備されていた」ことが、大きな混乱を防ぎ、住民の安心につながりました。
管理組合ができる「今すぐ始める防災」
では、何から始めればよいのでしょうか?以下に「今すぐできること」をいくつか挙げてみます。
-
共用部の防災点検の実施
-
非常口の確保、消火器の使用期限確認、防災設備の稼働チェック
-
-
防災マニュアルの作成・配布
-
避難経路、安否確認の方法、役割分担などを明文化
-
-
住民アンケートの実施
-
災害時の要配慮者(高齢者・障害のある方)の把握や、自主的な協力者の募集
-
-
防災倉庫の整備と定期見直し
-
古くなった備蓄品の更新、必要な物資の追加
-
-
小規模でも良いので防災訓練を実施
-
特に初動対応(避難誘導、安否確認)を中心に
-
防災は「イベント」ではなく「文化」へ
防災訓練を一度やったからといって、それで終わりではありません。定期的に見直し、継続して行うことが大切です。年に1回でも2回でも、防災の話題を住民間で共有し、関心を持ち続けること。これこそが、本当に災害に強いマンションをつくる「防災文化」への第一歩です。
マンションの防災は、管理という日常の延長線上にあります。少しずつ、でも確実に、日常の中に「防災の視点」を取り入れていくことで、私たちはいつ起きるか分からない「もしも」に対して、大きな備えをすることができるのです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
「防災は管理の延長線」——この考え方が、あなたのマンション、そして暮らし全体を守る大きな力になることを願って。