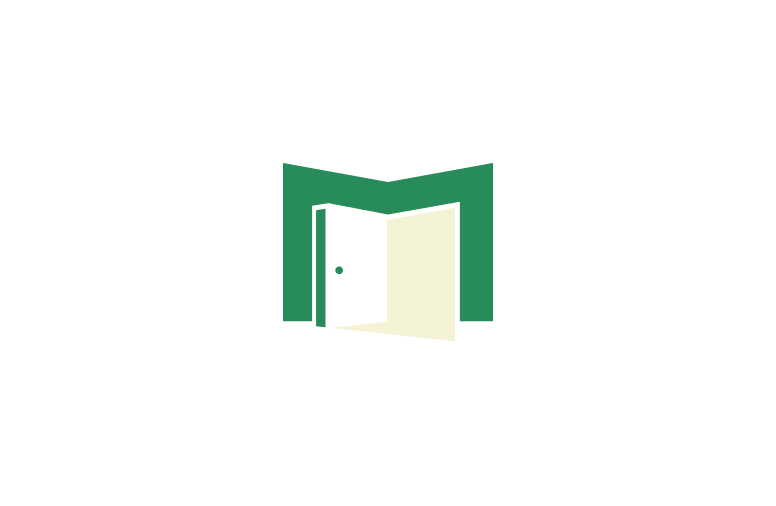マンション生活において“安全な水の供給”は基本でありながら、住民の目が届きにくく、管理が軽視されやすい分野です。特に「貯水槽方式」を採用しているマンションでは、水槽の維持管理が不十分なまま放置されることで水質事故のリスクが高まります。本稿では、区分所有マンションを対象に、貯水槽方式における清掃・法定検査の位置づけと、近年増えている「直結増圧給水方式」との違いを解説します。
■ マンションの給水方式とは?
給水方式 概要 特徴
貯水槽方式 地上の受水槽(+屋上の高置水槽)にいったん水を貯めて各戸へ供給 停電時も一時的に給水可能だが、貯水槽の管理が必要
直結増圧方式 水道本管の水を増圧ポンプで直接各戸に供給 設備が簡素、水質が新鮮、貯水槽が不要
■ 「簡易専用水道」とは?
次の条件を満たすマンションは水道法第34条の2に基づく簡易専用水道に該当します.
受水槽の有効容量が10m³を超える
建物利用者のみに供給する施設(=専用利用)
この場合、管理組合には年1回、登録検査機関による「法定検査」実施義務があります(厚生労働省登録機関が検査を実施)。
■ 法定の「簡易専用水道検査」内容
給水施設(受水槽、配管など)の外観確認
防虫・防鼠対策、密閉性の確認
水槽内部の衛生状態の確認
残留塩素濃度や濁度などの簡易水質検査
点検記録・清掃履歴の確認
※違反時には保健所より是正指導、場合によっては行政処分の対象となることもあります。
■ 貯水槽清掃は義務か?【明確な法的義務は“ない”】
ここが誤解されやすい点です。
水道法では「清掃義務」は明記されていない
一部の自治体(例:大阪市・名古屋市・横浜市など)は条例等で「年1回以上の清掃を“努力義務”もしくは“指導基準”」としているケースあり
しかし、全国的に見れば「明確な義務化」されている自治体は少数
したがって、「多くの自治体で義務化されている」→誤りです。お詫びして訂正します。
ただし、管理組合の善管注意義務(民法第644条)の観点から、以下のようなリスク管理のために年1回の清掃が強く推奨されます:
水槽内部の汚れや微生物の繁殖を抑制
苔・藻・虫の混入防止
清掃履歴がない場合の売却・賃貸時の信頼低下リスク回避
■ 直結増圧方式との比較
比較項目 貯水槽方式 直結増圧方式
水質管理 管理者が清掃・検査を行う必要あり 水道局の管理下で新鮮な水
停電時 一時的に給水可能(槽の水が残る) 給水不能になる可能性あり
維持コスト 清掃・検査などで定期支出あり 維持管理コストが軽減される
見た目・スペース 地上や屋上にタンクが必要 建物のスペースが有効活用できる
更新コスト 配管・槽の老朽化対応必要 更新費用は比較的少なめだが水道本管の条件に依存
■ 管理組合として取るべき対応
貯水槽の容量と構造を確認し、10m³を超える場合は「簡易専用水道」に該当
法定検査(年1回)を必ず実施し、記録を保管
清掃は法的義務ではないが、年1回の実施を推奨
老朽化・更新時期を見据え、直結方式への変更可能性を検討
住民への説明責任(安心・安全に配慮した運営)を果たす
■ まとめ
貯水槽清掃は義務ではないが、義務に準じた実務的対応が必要です。とくに区分所有マンションでは、給水事故が起きれば管理組合が責任を問われ、資産価値や管理の信頼性に直結します。
直結増圧方式への更新もひとつの選択肢ですが、すぐには切り替えられない物件も多いため、現行設備の下で法定検査+清掃の実施が最優先です。
「うちは検査してるから大丈夫」ではなく、検査も清掃も実施履歴を管理し、トラブルを未然に防ぐことが、管理組合に求められる基本姿勢といえるでしょう。