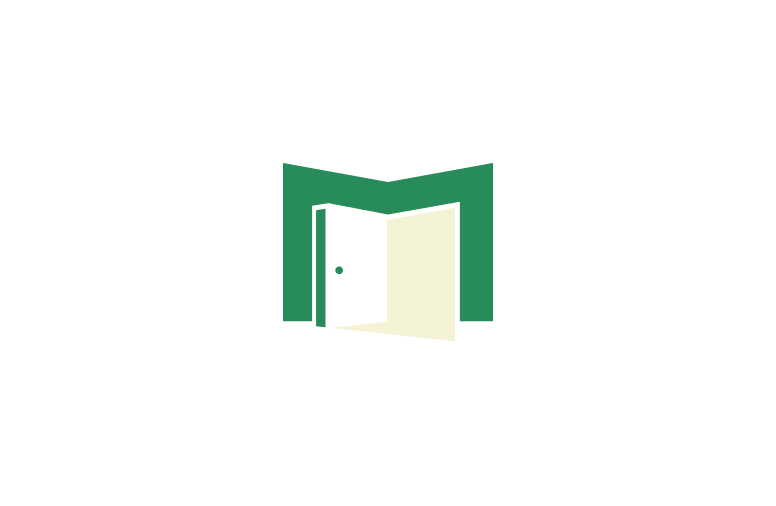※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
ある日ポストに届いた「管理費等改定のお知らせ」。毎月の支出が増えることに、多くの方が不安や疑問を感じるのではないでしょうか。管理会社からの値上げ要請は、一方的に受け入れるしかないのでしょうか?
この記事では、宅地建物取引士の視点から、マンション管理費の値上げを通知された際に、区分所有者が冷静に状況を判断し、適切に行動するためのステップを解説します。値上げの社会的背景から、確認すべき書類、法的な手続き、そして妥当性を検証する具体的な方法まで、網羅的にご紹介します。
本記事を読めば、値上げの根拠を正しく理解し、管理組合の一員として建設的な議論に参加できるようになります。単なるコスト増と捉えるのではなく、ご自身のマンションの資産価値と将来を見つめ直す機会としましょう。
なぜ今?マンション管理費が値上がりする4つの社会的背景

管理会社からの突然の値上げ通知に、「うちの管理会社だけが不当な要求をしているのでは?」と感じるかもしれません。しかし、その背景には個別の会社の問題だけでなく、社会全体に共通する構造的な要因が存在します。まずは、なぜ今、管理費の値上げが相次いでいるのか、その4つの大きな理由を理解しましょう。
1. 人件費の上昇(管理人・清掃員など)
マンション管理の品質は、管理人や清掃員といった現場のスタッフによって支えられています。彼らの人件費は、管理組合が管理会社に支払う「管理委託費」の大きな割合を占めています。
近年、全国的に最低賃金が引き上げられており、これが直接的に人件費の上昇につながっています(出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)。また、少子高齢化による労働力不足も深刻で、人材を確保するためには以前よりも高い賃金が必要となっているのです。
2. 物価・エネルギー価格の高騰
マンションの共用部分を維持するためには、電気、水道、ガスなどのエネルギーが不可欠です。エレベーターを動かし、廊下の照明を灯し、エントランスの空調を維持するための光熱費は、近年のエネルギー価格高騰の影響を直接受けます。
また、共用部分の電球交換や小規模な修繕に使う資材の価格、清掃に用いる消耗品の価格なども、全般的な物価上昇(出典:総務省統計局「消費者物価指数(CPI)」)に伴い上がっており、これらが管理コストを押し上げる要因となっています。
3. 築年数の経過とサービス内容の高度化
マンションも年を重ねるごとに、維持管理に必要な手間やコストが増加します。軽微な修繕の頻度が増えたり、旧式の設備を維持するための費用がかさんだりすることがあります。
さらに、宅配ボックスの設置、コンシェルジュサービスの導入、防犯カメラシステムの高度化など、住民のニーズに応える形で管理サービスの内容がリッチになる傾向もあります。これらのサービス向上は、当然ながら管理コストの増加につながり、管理費に反映されることになります。
4. 2022年以降の制度改正の影響
2022年4月に「マンション管理計画認定制度」が創設されて以降、30年以上の長期修繕計画や計画期間中の黒字維持が求められるようになり、修繕積立金の値上げ機運が全国的に高まっています(出典:長谷工「管理費・修繕積立金が値上げ! その理由と適正額の見極め方を聞いた」)。この動きは管理費とは別会計ですが、マンション管理全体のコスト意識を高め、管理の質を維持するための費用増に対する理解を促す背景となっています。
【ステップ1】まずは現状把握!値上げの根拠を書類で確認する
値上げの通知を受けたら、感情的に反発する前に、まずは事実を確認することが重要です。管理組合が保管している書類の中に、値上げの根拠を客観的に判断するための情報がすべて詰まっています。特に重要なのが次の2つの書類です。
① 管理委託契約書:どんな業務にいくら払っているか
管理組合と管理会社が交わしている「管理委託契約書」は、すべての基本となる書類です。ここには、管理会社に委託している業務の範囲と、その対価である「管理委託費」の内訳が明記されています。
- 事務管理業務費:会計、総会・理事会の運営支援など
- 管理人業務費:勤務形態(常駐・巡回)、勤務時間など
- 清掃業務費:清掃の範囲、頻度など
- 設備管理業務費:エレベーター、消防設備などの法定点検費用
値上げの提案が、どの業務項目に対するものなのかを特定することが第一歩です。
② 収支報告書・予算案:お金の流れと値上げの影響額
管理組合の「収支報告書」を見れば、前期の収入(管理費など)と支出(管理委託費、共用部光熱費など)の実績がわかります。そして、「予算案」には、来期の収入と支出の見込みが計上されています。
値上げ案が承認された場合、予算案の支出項目(主に管理委託費)がどれだけ増えるのか、そしてその結果、管理組合の財政がどうなるのか(赤字にならないか)を確認しましょう。
③【重要】「管理費」と「修繕積立金」は別モノです
ここで、非常に重要な用語の整理をしておきましょう。多くの人が混同しがちですが、「管理費」と「修繕積立金」は全くの別物です。
| 費用項目 | 目的・使途 | 会計 |
|---|---|---|
| 管理費 | 日常的な維持管理(清掃、管理人業務、共用部の光熱費、小修繕など) | 管理費会計 |
| 修繕積立金 | 将来の大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、給排水管更新など) | 修繕積立金会計 |
今回、管理会社から値上げを要請されているのは、管理組合が管理会社に支払う「管理委託費」です。この原資は、皆さんが支払う「管理費」から賄われます。したがって、管理委託費の値上げが承認されれば、結果として各区分所有者が支払う管理費の増額につながる、という関係性を正しく理解することが重要です。
【ステップ2】手続きは適正?値上げに必要な総会のルール

管理費(厳密にはその原資となる管理委託費)の値上げは、管理会社が一方的に決定できるものではありません。必ず、マンションの最高意思決定機関である「総会」での決議が必要です。その手続きが法規や規約に則って正しく行われているかを確認しましょう。
原則は「普通決議」での承認が必要
管理委託費の増額を含む「収支予算案」の承認や変更は、原則として総会の「普通決議」によって決まります。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
(出典:建物の区分所有等に関する法律 第三十九条第一項)
※以下、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)を「区分所有法」と表記します。
つまり、出席した区分所有者の頭数と、その議決権(通常は専有部分の床面積割合)の両方で過半数の賛成が得られれば、議案は可決されます。
規約自体の変更なら「特別多数決議」に
注意が必要なのは、マンションの管理規約で「管理費は専有部分1㎡あたり〇〇円とする」のように、具体的な単価が定められている場合です。この規約の条文自体を変更するには、より要件の厳しい「特別多数決議」が必要となります。
規約の設定、変更及び廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。(後略)
(出典:建物の区分所有等に関する法律 第三十一条第一項)
【宅建士からの注意】
決議要件は、区分所有法が原則を定めていますが、個別のマンションの管理規約で別段の定めをすることも可能です。必ずご自身のマンションの管理規約を確認してください。
議事録を確認し、過去の経緯を把握する
値上げの提案が今回初めてなのか、それとも過去にも議論があったのかを知るために、過去の総会議事録を確認することも有効です。どのような経緯で現在の管理委託費が設定されたのか、過去に値上げを見送った経緯はないかなどを把握することで、今回の提案の背景をより深く理解できます。
【ステップ3】値上げ額は妥当?客観的に判断する3つの検証方法
手続きの正当性を確認したら、次は「値上げ額そのもの」が妥当かどうかを検証します。感情論ではなく、客観的なデータに基づいて判断することが重要です。
① 過去の会計報告と項目別に比較する
まずは、値上げ提案の根拠となっている見積書と、過去数年分の収支報告書を並べて、項目ごとに金額を比較します。「管理委託費」と一括りにせず、「管理人業務費」「清掃業務費」「設備管理業務費」といった内訳で比較することで、どの部分が、どれくらい上昇しているのかが一目瞭然になります。特に上昇率が高い項目について、管理会社に具体的な根拠(例:最低賃金の上昇率、特定の点検費用の市況など)を説明してもらいましょう。
② 国土交通省の統計データと乖離がないか確認する
国土交通省が定期的に公表している「マンション総合調査」は、ご自身のマンションの管理費水準を客観視する上で参考になります。
| 項目 | 平成30年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 管理費(月額/戸) | 15,956円 | 16,213円 |
ご自身のマンションの管理費がこの平均値と比べてどうなのかを確認してみましょう。ただし、これはあくまで全国平均です。マンションの規模、立地、設備、サービスの質によって適正な水準は大きく異なるため、このデータだけで「高い」「安い」と断定はできません。あくまで参考値として捉え、乖離が大きい場合はその理由を考えてみることが大切です。
③ 管理会社の見直しも視野に「相見積もり」を取得する
現在の管理会社からの値上げ提案が妥当かどうかを判断する最も有効な手段の一つが、他の管理会社から「相見積もり」を取得することです。同じ業務内容・仕様で見積もりを依頼することで、現在の管理委託費や値上げ提案額が、市場価格と比較して適正な範囲にあるのかを客観的に評価できます。相見積もりは、理事会が主体となって進めるのが一般的です。
値上げに納得できない…総会前後にできること

書類を確認し、客観的な検証を行った上で、それでも値上げに納得できない点がある場合、どのように行動すればよいのでしょうか。
理事会や総会で質問・議論すべきポイント
管理組合の一員として、理事会や総会で積極的に質問し、議論に参加することが重要です。その際は、以下のようなポイントを整理しておくと、建設的な対話につながります。
- 値上げの根拠:「管理人業務費が〇%上昇している理由は、最低賃金の上昇率△%と比較して妥当ですか?」
- コスト削減努力:「共用部の照明をLED化するなど、管理組合側でできるコスト削減策は検討しましたか?」
- 業務仕様の見直し:「清掃頻度を週5日から週4日に見直した場合、コストはどの程度削減できますか?」
- 長期的な視点:「今回の値上げは、今後も継続するのでしょうか?中期的な費用見通しはありますか?」
感情論はNG!データに基づいた対話を
「とにかく値上げは反対だ」といった感情的な主張だけでは、議論は進展しません。ここまで確認してきた書類やデータを基に、「この部分の根拠が不明確だ」「この業務は過剰ではないか」といった具体的な指摘をすることが、管理会社や他の区分所有者の理解を得るための鍵となります。値上げは管理組合と管理会社が健全なパートナーシップを築くための交渉の場と捉えましょう。
【要注意】管理会社の見直し(リプレイス)で失敗しないために

相見積もりは有効な手段ですが、安易なコストカットだけを目的とした管理会社の変更(リプレイス)には注意が必要です。失敗しないための3つのポイントを押さえておきましょう。
過度な相見積もりは敬遠されるワナ
コストを比較したいあまり、5社も6社も相見積もりを依頼する管理組合がありますが、これは逆効果になることが多いです。管理会社にとって、正確な見積もりを作成するには、現地調査、図面確認、協力会社との調整など、多大な時間と労力がかかります。過度に多くの会社を競わせる組合は、「手間がかかるだけで受注できる可能性が低い」と判断され、真摯な提案が集まりにくくなる傾向があります。現実的な相見積もりの相手は、3~5社程度に絞るのが望ましいとされています。(出典:一般社団法人マンション管理ナビ埼玉)
「一式見積もり」を避けるべき理由
見積もりを依頼する際に、注意したいのが「一式〇〇円」という記載です。
「一式見積もり」では、どの業務にいくらかかっているのかが全く分かりません。これでは、各社の提案を公平に比較検討することができず、不透明なコスト計上の温床にもなります。
適正な比較のためには、必ず現行の管理委託契約書の内訳項目に沿って、詳細な見積もりを提出するよう依頼しましょう。業務仕様書や共通の見積もりフォーマットを用意すると、より比較が容易になります。
管理会社側の労力も理解する視点
管理会社は、単に机上で数字を計算しているわけではありません。前述の通り、見積もり作成には複数回の現地調査や、清掃・設備点検など各協力会社との打ち合わせ、理事会へのヒアリングなど、多大な労力がかかっています。
相見積もりを依頼する際は、こうした管理会社側の労力にも配慮し、誠実な態度で接することが、結果として質の高い提案を引き出し、良好なパートナーシップを築く上で非常に重要です。
まとめ:管理費の値上げは、マンションの将来を考える良い機会

マンション管理費の値上げ通知は、家計にとって決して嬉しいものではありません。しかし、これを単なる「負担増」と捉えるのではなく、自分たちの資産であるマンションの管理のあり方を見つめ直す絶好の機会と捉えることが大切です。
- 社会的背景を理解し、冷静に受け止める。
- 管理委託契約書や収支報告書で、事実を客観的に把握する。
- 総会決議という適正な手続きの重要性を認識する。
- データや相見積もりを基に、値上げ額の妥当性を検証する。
- 建設的な対話を通じて、管理の質とコストの最適バランスを探る。
これらのステップを踏むことで、あなたは単なる居住者から、マンションの資産価値を主体的に維持・向上させる「管理組合の一員」へと変わることができます。今回の値上げが、あなたのマンションにとってより良い未来を築くための第一歩となることを願っています。
免責事項
本記事は、マンション管理費に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件や個別の事案に対する法的助言を行うものではありません。管理費の改定に関する最終的な判断は、区分所有法や当該マンションの管理規約、総会の決議等に基づいて行われる必要があります。最新の法令や、ご自身のマンションの管理規約・契約内容を必ずご確認ください。
参考資料
- デジタル庁 e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069 - 国土交通省「マンション管理計画認定制度について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000001.html - 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html - 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html - 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ - 総務省統計局「消費者物価指数(CPI)」
https://www.stat.go.jp/data/cpi/ - 長谷工「管理費・修繕積立金が値上げ! その理由と適正額の見極め方を聞いた」
https://www.haseko.co.jp/mansionplus/journal/kanrihi-syuzen-250416.html - 一般社団法人マンション管理ナビ埼玉「管理会社に相見積もりを依頼する時の注意点」
https://www.mansionkanri-navi-saitama.com/kannrikaisyatoha/cost-estimate.html
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。