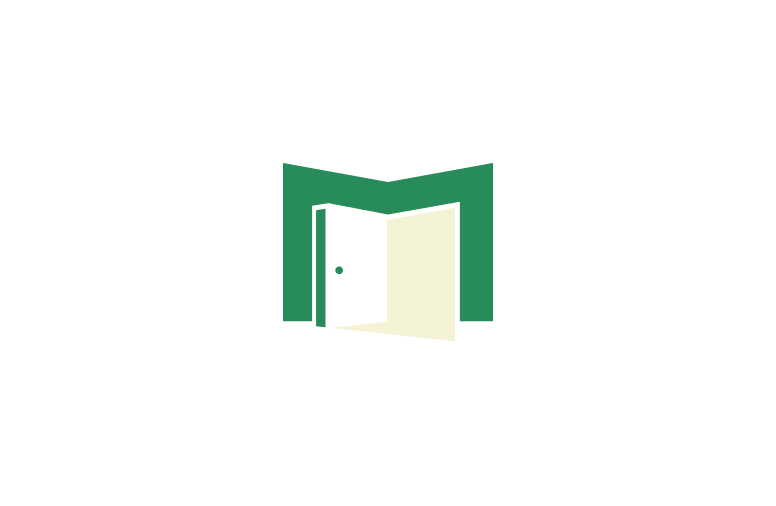※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
(2025年10月17日時点での最新情報確認済み)
本記事は、国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」(2024年6月21日公表)を最新の公的統計として参照しています。同調査は概ね5年ごとに実施されるため、次回調査結果の公表時期(令和10年度頃と予想)には情報が更新される可能性があります。
自主管理マンションは、管理会社に支払う委託費用を削減できる大きなメリットがあります。しかし、そのコスト削減の裏側には、専門知識の不足から生じる「会計」「運営」「建物維持」「法務・対人」という4つの重大なリスクが潜んでいます。これらのリスクを放置すると、管理費の滞納や修繕積立金の不足を招き、最悪の場合、マンションの資産価値を大きく損なうことになりかねません。
この記事では、宅地建物取引士の資格を持つ不動産ライターが、国土交通省の公表データや法令に基づき、自主管理マンションが直面する具体的なリスクと、それらを回避・軽減するための実践的な対策を徹底解説します。現在、理事や役員を務めている方、これから役員になる可能性のある方は、ぜひご一読ください。
はじめに:自主管理マンションとは?コスト削減の裏にある潜在リスク

マンションの管理方式は、大きく「自主管理」と「委託管理」に分けられます。まずは両者の基本的な違いと、なぜ今、自主管理のリスクが注目されているのかを理解しましょう。
自主管理と委託管理の基本的な違い
自主管理とは、管理会社に業務を委託せず、マンションの区分所有者で構成される「管理組合」が主体となって、会計、清掃、点検、修繕計画の策定といった管理業務のすべてを行う方式です。一方、委託管理は、これらの業務の全部または一部を専門の管理会社に委託する方式を指します。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 自主管理 | 委託管理 |
|---|---|---|
| メリット | ・管理委託費がかからず、コストを削減できる ・管理組合の意向を運営に直接反映させやすい | ・専門知識を持つプロに業務を任せられる ・役員の業務負担が大幅に軽減される ・滞納督促やトラブル対応のノウハウがある |
| デメリット | ・役員の業務負担が非常に大きい ・専門知識(会計、法律、建築)が不足しがち ・役員のなり手不足や属人化に陥りやすい ・トラブル対応が当事者間で行われ、こじれやすい | ・管理委託費用が発生する ・管理会社の対応品質にばらつきがある ・管理会社の変更手続きが煩雑な場合がある |
自主管理は、必要な業務だけを清掃業者や会計士など個別の専門家に「一部委託」することも可能で、運営の自由度が高い点が特徴です。
なぜ今、自主管理のリスクが注目されるのか?
近年、自主管理マンションのリスクが注目される背景には、建物の高経年化と居住者の高齢化という社会的な問題があります。 役員のなり手が不足し、これまで運営を担ってきた中心人物が引退すると、蓄積されたノウハウが失われ、管理が機能不全に陥るケースが増えています。専門知識を欠いたまま運営を続けることで、後述する様々なリスクが顕在化し、気づいた時には手遅れになっていることも少なくありません。
【会計リスク】管理費滞納とずさんな会計処理が資産を蝕む

マンション管理の根幹である会計業務。ここに問題が生じると、マンション全体の資産価値に直接影響します。
リスク①:管理費・修繕積立金の滞納と徴収の困難さ
自主管理マンションで最も発生しやすいのが、管理費や修繕積立金の滞納問題です。国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」(調査時点:令和5年10月~令和6年3月、公表:令和6年6月21日)によれば、管理費等を3ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合の割合は29.2%にのぼります(同調査報告書p.41)。これは平成30年度調査の24.4%から4.8ポイント増加しており、滞納問題が深刻化していることがわかります。
委託管理であれば管理会社が督促業務を代行しますが、自主管理では理事自らが同じマンションの住民に支払いを催促しなければなりません。人間関係への配慮から強い督促ができず、滞納が長期化・深刻化しやすい傾向があります。
リスク②:会計担当者の知識不足による会計処理ミス
管理組合の会計は、「管理費」と「修繕積立金」を明確に分けて管理(分別管理)する必要があります。
- 管理費: 日常の清掃、共用部の光熱費、小規模な修繕などに充当
- 修繕積立金: 将来の大規模修繕工事のために積み立てる資金
会計知識が不十分な担当者が、資金不足を理由に修繕積立金を管理費の補填に安易に流用してしまうと、将来の修繕計画が破綻する原因となります。これは管理組合の役員が負うべき「善良な管理者の注意義務」(後述)に違反する可能性のある、重大な問題です。
リスク③:横領の発生とチェック機能の不在
会計業務が一人の担当者に集中し、他の役員がチェックしない「ブラックボックス化」した状態は非常に危険です。通帳、印鑑、キャッシュカードをすべて一人が管理している場合、横領のリスクが格段に高まります。
【実務上のチェックポイント】
横領を防ぐためには、最低でも以下の体制を構築することが不可欠です。
・通帳は理事長、印鑑は会計担当、キャッシュカードは監事など、複数人で分散して保管する。
・監事は定期的に通帳や領収書を監査し、理事会で報告する。
・可能であれば、年1回以上、外部の税理士または公認会計士による会計監査を受けることも検討する。
チェック機能が働かないずさんな会計管理は、組合の財産を危険に晒す行為です。
【運営リスク】役員の負担増大とコミュニティの形骸化
管理組合の運営そのものにも、自主管理特有のリスクが存在します。
リスク①:理事のなり手不足と業務の属人化
会計、総会準備、業者との折衝、トラブル対応など、自主管理の役員の業務は多岐にわたり、非常に大きな負担がかかります。その結果、「誰もやりたがらない」というなり手不足の問題が発生します。実際、国土交通省「令和5年度マンション総合調査」では、管理組合が抱える課題として「役員のなり手不足」を挙げた割合は42.3%に上っています。
特定の意欲ある人に業務が集中する「属人化」も深刻です。その人が転居や高齢化で役員を続けられなくなった途端、管理組合の運営が立ち行かなくなるリスクを常に抱えています。
リスク②:総会・理事会の形骸化と意思決定の遅延
役員の負担が大きいと、総会や理事会の準備が不十分になりがちです。議題の整理や資料作成が間に合わず、議論が深まらないまま時間だけが過ぎていく、といった形骸化が進みます。 その結果、重要な修繕工事の決定などが先送りされ、建物の劣化を加速させることにも繋がりかねません。
リスク③:住民間の合意形成の難航
自主管理は住民の意見が直接反映されやすい反面、意見がまとまらないリスクもあります。特に大規模修繕のように多額の費用がかかる議題では、住民間の利害が対立し、合意形成が難航することが少なくありません。 専門家である管理会社が介在しないため、客観的なデータに基づいた議論が難しく、感情的な対立に発展しやすいのも特徴です。
【建物維持リスク】専門知識の欠如が招く資産価値の低下

建物の維持管理には高度な専門知識が不可欠です。この知識不足が、マンションの資産価値を直接的に低下させるリスクにつながります。
リスク①:不適切な長期修繕計画と積立金不足
マンションの資産価値を維持するためには、計画的な修繕が不可欠です。国土交通省は「長期修繕計画作成ガイドライン」で、30年以上の長期的な計画を策定し、5年程度ごとに見直すことを推奨しています。 しかし、建築の専門知識がない役員だけで適切な計画を立てるのは極めて困難です。計画が甘ければ、いざ大規模修繕という時に積立金が大幅に不足し、一時金を徴収したり、工事の質を落とさざるを得ない事態に陥ります。
リスク②:不適切な業者選定による品質低下・コスト増
修繕工事や設備点検の業者選定も、専門知識が問われる重要な業務です。相見積もりを取っても、提示された仕様や金額が妥当かどうかを判断できず、安かろう悪かろうの業者を選んでしまうリスクがあります。 特に「工事一式」といった内訳が不明瞭な見積もりは危険です。後から追加費用を請求されたり、手抜き工事をされたりする温床となり、結果的にコスト増や品質低下を招きます。
リスク③:法定点検・報告義務の履行漏れ
建築基準法や消防法などに基づき、マンションは定期的な点検を行い、特定行政庁へ報告する義務があります。 これらの法定点検を怠ると、是正勧告を受けたり、万が一事故が発生した際に管理組合が重大な責任を問われたりする可能性があります。専門家のサポートがない自主管理では、こうした法的な義務をうっかり履行し忘れるリスクがあります。具体的には、以下のような点検が義務付けられています。
- 特殊建築物等定期調査(建築基準法第12条)
- 建築設備定期検査(同法第12条)
- 消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)
- エレベーター定期検査(建築基準法第12条)
【法的・対人トラブルリスク】法律違反と住民間トラブルへの対応遅延

管理組合の運営は、区分所有法や民法といった法律と密接に関わっています。法律知識の不足は、思わぬトラブルを招きます。
リスク①:区分所有法など関連法令の遵守漏れ
管理費を長期滞納する住民に対し、最終手段としてその住戸の競売を請求する手続きがあります。これは区分所有法第59条に定められていますが、実行するには「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」の特別決議が必要です(ただし、管理規約に別段の定めがある場合はその定めに従います)。 こうした法的手続きや決議要件を知らないまま対応が遅れると、滞納額が膨らみ、回収が極めて困難になります。
リスク②:役員が負う法的責任(善管注意義務違反)の重大性
管理組合の役員は、たとえボランティアであっても、法律上の重い責任を負っています。それが善管注意義務(善良な管理者の注意義務)です。
| (根拠条文) ・民法 第644条:「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」 ・建物の区分所有等に関する法律(区分所有法) 第28条:管理者の権利義務等について定めており、この規定により管理組合の管理者(理事など)にも民法第644条が準用され、善管注意義務を負います。 |
これは、「役員の立場にある者として、客観的に見て通常期待される注意を払う義務」を意味します。例えば、必要な修繕を怠って建物に損害を与えたり、会計処理を誤って組合に金銭的損失を与えたりした場合、役員個人が組合に対して損害賠償責任(任務懈怠責任)を問われる可能性があります。
リスク③:騒音・マナー違反など住民間トラブル対応の限界
騒音、ペット問題、ゴミ出しルール違反など、住民間のトラブルはどのマンションでも起こり得ます。委託管理であれば管理会社が中立的な立場で一次対応を行いますが、自主管理では役員が直接、当事者の間に入って対応しなければなりません。 感情的になりがちな住民同士の争いに巻き込まれ、精神的に疲弊してしまうケースも少なくありません。
自主管理のリスクを回避・軽減する5つの具体的対策

ここまで解説したリスクは、適切な対策を講じることで回避・軽減が可能です。
対策①:外部専門家(マンション管理士など)の活用
すべての業務を自分たちで行うことに固執せず、専門家の力を借りることが最も有効な対策です。特にマンション管理士は、管理組合の運営をサポートする専門家であり、良き相談相手となります。 契約形態には、継続的にアドバイスを受ける「顧問契約」と、規約改正や大規模修繕など特定の課題について相談する「スポット契約」があります。
対策②:会計・運営支援ツールの導入
近年、管理組合向けのクラウド会計ソフトやコミュニケーションツールが登場しています。これらを導入することで、会計処理の透明化や情報共有の効率化が図れ、役員の負担を軽減できます。
対策③:管理規約の定期的な見直しと周知徹底
管理規約はマンションの憲法です。役員の役割や選任方法、トラブル発生時の対応ルールなどを明確に定めておくことで、運営がスムーズになります。国土交通省の「マンション標準管理規約」を参考に、定期的に内容を見直しましょう。
対策④:一部業務の外部委託(会計・清掃など)
専門性が高く負担の大きい業務は、部分的に外部へ委託する「一部委託」も有効な選択肢です。特に手間のかかる会計業務や日常の清掃業務を委託するだけでも、役員の負担は大きく変わります。
対策⑤:役員の負担を軽減するルールの整備(輪番制、報酬設定など)
役員のなり手不足対策として、全戸で役員を順番に担当する「輪番制」や、役員に一定の報酬を支払う制度を導入することも検討に値します。負担の公平化を図り、協力体制を築くことが重要です。
コラム:マンション管理計画認定制度とは?
令和4年(2022年)に施行された改正マンション管理適正化法に基づき、地方公共団体が管理組合の管理計画を認定する制度です。認定を受けると、住宅金融支援機構の「フラット35」における金利引き下げなどのメリットがあります。 ※この制度はマンション(管理組合)の管理計画を評価するものであり、管理会社を評価・ランク付けする制度ではありませんのでご注意ください。詳細については、国土交通省のウェブサイト等で最新の情報をご確認ください。
限界を感じたら?自主管理から委託管理への移行を検討する手順

様々な対策を講じてもなお運営に限界を感じる場合は、全部委託管理への移行を本格的に検討しましょう。
Step1:移行検討の総会決議
まずは「委託管理への移行を検討すること」について、総会で決議(普通決議。ただし、管理規約に別段の定めがある場合はその定めに従う)を得ます。ここで住民の合意を得ておくことで、その後の手続きがスムーズに進みます。
Step2:管理会社の選定と見積もり依頼
複数の管理会社に声をかけ、管理委託費の見積もりを依頼します。この際、実務上、5社以上への過度な見積依頼は管理会社側の負担が大きく、提案品質の低下を招く可能性があるため、信頼できそうな会社を2~3社程度に絞って比較検討することが、業界実務では一般的とされています。
管理会社は、正確な見積もりを作成するために現地調査や各種点検会社との調整など、多大な労力をかけます。特に小規模なマンションの場合、過度な相見積もりは敬遠され、質の高い提案を受けにくくなる可能性があることを理解しておきましょう。
Step3:見積もり比較のポイント(「一式」はNG)
提出された見積もりを比較する際は、金額の安さだけで判断してはいけません。以下の点をチェックしましょう。
- 業務内容: どこまでが委託範囲に含まれているか(基幹事務は全て含まれるか)
- 見積もりの内訳: 「管理委託費一式」ではなく、事務管理費、管理員業務費、清掃費、設備管理費などの内訳が詳細に記載されているか
- 緊急時対応: 24時間対応のコールセンターはあるか、対応体制はどうか
- 担当者の対応: 説明は丁寧か、質問に的確に答えられるか
Step4:契約締結と引き継ぎ
管理会社が決まったら、総会で承認決議(普通決議。ただし、管理規約に別段の定めがある場合はその定めに従います)を得て、管理委託契約を締結します。契約内容は、国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」と照らし合わせ、組合にとって不利な条項がないか確認しましょう。なお、契約の更新・解約・変更に関する条項については、締結後は当該契約書の定めが最優先されます。
契約後は、これまでの会計資料や点検記録などを管理会社へ引き継ぎます。
まとめ:リスクを正しく理解し、最適な管理体制を目指そう

自主管理はコスト削減という魅力的なメリットがある一方、専門知識の不足が原因で「会計」「運営」「建物維持」「法務・対人」の4つの側面で重大なリスクを抱えています。
- 会計リスク: 滞納の増加、ずさんな会計処理、横領の危険性
- 運営リスク: 役員のなり手不足、業務の属人化、意思決定の遅延
- 建物維持リスク: 不適切な修繕計画による積立金不足、資産価値の低下
- 法的・対人リスク: 法令違反や役員の善管注意義務違反、住民間トラブルの悪化
これらのリスクを正しく理解し、専門家の活用や一部委託、運営ツールの導入といった対策を早期に講じることが、マンションの資産価値を守る上で不可欠です。もし自主管理の継続が困難だと感じた場合は、委託管理への移行も視野に入れ、管理組合全体で最適な管理体制を話し合っていきましょう。
自主管理マンションに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 自主管理の最大のメリットは何ですか?
A1. 最大のメリットは、管理会社に支払う管理委託費用がかからないため、管理費や修繕積立金の額を低く抑えられる可能性がある点です。また、管理組合の意向をダイレクトに運営へ反映させやすいという利点もあります。
Q2. 理事のなり手がいない場合、どうすればよいですか?
A2. いくつかの対策が考えられます。①役員の業務負担を軽減するため、会計業務などを部分的に外部委託する、②輪番制を導入して負担を公平化する、③役員に報酬を支払う制度を設ける、④マンション管理士などの専門家に相談し、運営サポートを依頼する、といった方法があります。最終的な手段として、全部委託管理への移行も選択肢となります。
Q3. 管理費を滞納されたら、まず何をすべきですか?
A3. まずは書面で滞納の事実と金額を通知し、支払いを丁寧に督促します。それでも支払いがない場合は、内容証明郵便を送付するなど、段階的に対応を強めていく必要があります。長期化しそうな場合や法的手続きを検討する際は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
免責事項(必読)
- 本記事は、2025年10月17日時点で公開されている情報に基づき、自主管理マンションに関する一般的な情報提供を目的として作成されたものです。
- 本記事は、特定のマンションにおける個別具体的な法的助言、会計処理指導、契約内容の判断を行うものではありません。
- 実際の管理組合の運営、決議要件、役員の権限・責任範囲、会計処理については、必ず以下を確認してください:
- 貴マンションの現行管理規約(最新版)
- 締結済みの各種契約書の条項
- 最新の法令(施行日・附則を含む)
- 個別事案への対応や法的判断が必要な場合は、弁護士、マンション管理士、税理士等の有資格専門家に直接ご相談ください。
- 本記事の情報により生じた一切の損害について、当サイトは責任を負いかねます。
参考資料
- 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」, 令和6年6月21日公表, (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000143.html)
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」, (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069)
- e-Gov法令検索「民法」, (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
- 国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」, 令和3年9月改訂(2021年), (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000033.html)
- 国土交通省「マンション標準管理委託契約書」, (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000053.html)
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。