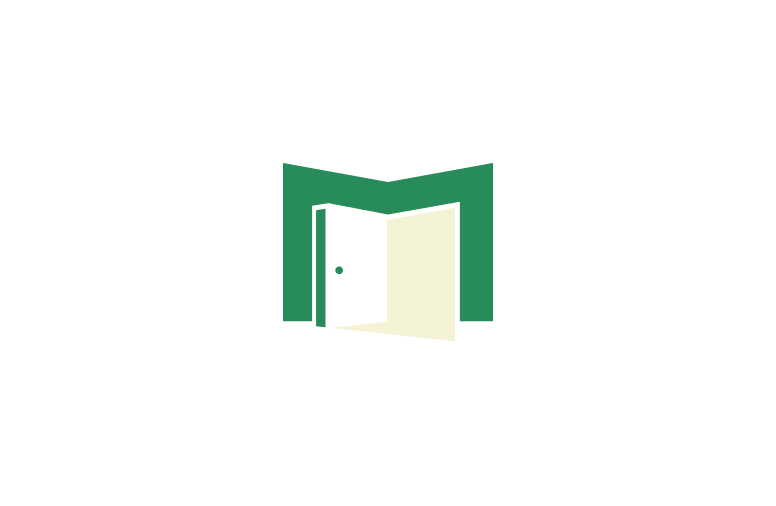※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
輪番制などで突然、自主管理マンションの理事長に就任され、何から手をつければ良いのか、どのような責任が伴うのか、不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。特に法律や会計の専門知識がない場合、そのプレッシャーは計り知れません。
この記事では、宅地建物取引士の知見を活かし、自主管理マンションの理事長が最低限知っておくべき法的知識、具体的な仕事内容、そして頻発するトラブルへの対処法を、最新の法令や国土交通省の資料に基づき網羅的に解説します。
本記事は、2025年10月16日時点の法令に基づき執筆しています。
理事長の役割を正しく理解し、一人で抱え込まずに適切な対策を講じることで、その重責は管理可能な業務へと変わります。この記事が、あなたの不安を解消し、円滑な管理組合運営の一助となれば幸いです。
はじめに:自主管理マンションの理事長就任、その不安を解消します

自主管理マンションの理事長就任、誠にお疲れ様です。管理会社に委託せず、住民自身で運営を行う自主管理は、コストを抑えられる一方で、理事、特に理事長には大きな責任と業務負担が伴います。
「法律なんてわからない」「住民同士のトラブルにどう介入すればいいの?」「もし何かあったら個人で責任を負うの?」といった不安は、多くの新任理事長が抱える共通の悩みです。
しかし、ご安心ください。理事長の責任範囲は法律で明確に定められており、やるべき業務も標準的なモデルが存在します。そして何より、すべての問題を一人で解決する必要はありません。
本記事では、理事長の役割を分解し、一つ一つの業務やリスクにどう向き合うべきかを具体的に解説します。法的根拠に基づいた正しい知識を身につけ、外部の専門家やサービスを賢く活用することで、理事長の負担は大幅に軽減できます。まずはご自身の法的な立ち位置から確認していきましょう。
まずは法的立ち位置を理解する:理事長の責任と権限の範囲

理事長の業務を始める前に、ご自身の法的な立ち位置、つまり「権限」と「責任」の範囲を正確に理解することが極めて重要です。これにより、過度な不安を解消し、同時に無自覚なリスクを回避できます。
理事長と管理組合の関係は「委任契約」
まず、法律上の重要な関係性を整理しましょう。
- 管理者と理事長:建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)では、管理組合の代表者を「管理者」と定めています。多くのマンション管理規約では、この「管理者」を「理事長」と定めることで、理事長が法律上の代表者となります。
- 管理組合と理事長:管理組合(区分所有者全員で構成される団体)と理事長(管理者)の関係は、民法上の「委任契約」にあたると解釈されています(民法第643条)。組合員からマンション管理という事務処理を委任されている、という立場です。
つまり理事長は「大家さん」ではなく、組合員全体の代理人として、委任された業務を執行する立場にあるのです。
負うべき責任:「善管注意義務」とは?
委任契約を結ぶと、理事長には「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」という責任が生じます(民法第644条)。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(出典:e-Gov法令検索「民法」)
これは、「理事長という立場や職務において、一般的に期待される水準の注意を払って業務を行う義務」を意味します。超人的な能力や完璧な結果を求められるわけではありません。標準的な注意を怠り、その結果として管理組合に損害を与えた場合に、責任を問われる可能性がある、と理解してください。
理事長個人の責任が問われるケース・問われないケース
では、具体的にどのような場合に個人の責任が問われるのでしょうか。
責任が問われないケース(原則)
- 法律や管理規約、総会決議に基づき、適正に業務を執行している場合。
- 理事会で十分に議論し、議事録を残した上で決定した事項を実行した場合。
- 業務の結果として組合に損失が生じたとしても、その判断過程で善管注意義務を果たしていれば、通常は個人責任を負いません。
責任が問われる可能性があるケース(例外)
- 明らかな法令・規約違反:理事会や総会の決議を経ずに、独断で多額の契約を結ぶなど。
- 義務の懈怠:長期修繕計画の見直しを何年も放置し、建物の劣化を招いた場合。
- 監督責任の放棄:会計担当の理事が組合費を横領している兆候があったにもかかわらず、確認を怠り放置した結果、損害が拡大した場合。
過去の裁判例では、会計担当の横領を見過ごした理事長に対し、損害額の一部について賠償責任を認めたケースもあります。ただし、これはあくまで職務を著しく怠った場合の例外的なケースです。誠実に業務に取り組んでいれば、過度に恐れる必要はありません。
※本判例は特定の事案に基づくものであり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。個別の状況については弁護士にご相談ください。
理事長の具体的な仕事内容【年間業務カレンダー】
理事長の業務は多岐にわたりますが、年間を通じて行うべき主要な業務は決まっています。ここでは、国土交通省が示す「マンション標準管理規約」を基に、理事長の4大業務を解説します。
① 総会・理事会の運営(招集・議事進行・議事録作成)
管理組合の最高意思決定機関である「総会」と、業務執行機関である「理事会」の運営は、理事長の最も重要な仕事です。
- 総会の招集・議長:理事長は、毎年1回、会計年度終了後一定期間内(標準管理規約では2ヶ月以内)に通常総会を招集する義務があります(マンション標準管理規約 第42条)。また、総会の議長を務め、議事を進行します。
- 理事会の招集・議長:理事会を必要に応じて(多くのマンションでは月1回程度)招集し、議長として議論をまとめます。
- 議事録の作成・保管:総会や理事会の後、議事録を作成し、議長および出席した理事が署名押印します。この議事録は、組合員や利害関係者(購入検討者など)からの閲覧請求に応じられるよう、適切に保管する義務があります(マンション標準管理規約 第49条、第54条)。
【重要】総会決議の要件は管理規約が最優先
以下の表は区分所有法に定める原則です。ただし、区分所有法第39条第1項により、管理規約で普通決議の要件を過半数より厳しく、または緩やかに定めることができます。特別決議の区分所有者数要件も、規約で過半数まで緩和可能です(議決権要件は緩和不可)。
重要な議案を扱う前には、必ず自マンションの管理規約で定められた決議要件を確認してください。
| 決議の種類 | 法定要件(原則) | 規約での変更可否 | 主な対象議案の例 |
|---|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者数および議決権の各過半数 | ○ 変更可 | ・予算、決算の承認 ・理事、監事の選任、解任 ・使用細則の制定、変更 |
| 特別決議 | 区分所有者数および議決権の各4分の3以上 | △ 区分所有者数のみ過半数まで緩和可 | ・管理規約の制定、変更、廃止 ・共用部分の重大な変更 |
| 建替え決議 | 区分所有者数および議決権の各5分の4以上 | × 変更不可 | ・建替え |
(出典:区分所有法、マンション標準管理規約を基に作成)
ご自身のマンションの管理規約で、これらの決議要件が変更されている場合があります。重要な議案を上程する前には、必ず規約を確認してください。
② 会計業務の監督(予算・決算案の承認、収支状況の確認)
会計担当の理事が実務を行う場合でも、理事長には組合財産全体を監督する最終的な責任があります。
- 予算案・決算案の承認:会計担当が作成した次年度の収支予算案と、当該年度の収支決算案を理事会で審議し、総会に提出します。決算案は、監事による会計監査を経る必要があります(マンション標準管理規約 第59条、第61条)。
- 収支状況の月次確認:管理費や修繕積立金の収納状況、各種経費の支払い状況などを月次報告書で確認し、組合の財政状況を常に把握します。
- 滞納者への督促:管理費の滞納が発生した場合、その督促を行うのは理事長の重要な職務です。
③ 建物・設備の維持管理(長期修繕計画の推進)
マンションの資産価値を維持するため、計画的な修繕は不可欠です。
- 長期修繕計画の管理:多くのマンションでは、将来の大規模修繕工事に備えて「長期修繕計画」が策定されています。理事長は、この計画が適切に運用・見直しされているかを確認する責任があります。国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」(令和3年9月改訂)では、以下の基準が示されています。
- 計画期間:25年以上
- 見直し周期:5年程度
- 日常的な維持管理の監督:共用部分の清掃、消防設備やエレベーターの法定点検などが、契約通りに実施されているかを確認します。
④ 規約・帳票類の保管と閲覧対応
理事長は、管理組合の重要書類を保管し、正当な理由を持つ組合員や利害関係者からの閲覧請求に対応する義務があります。
- 保管すべき書類の例:
- 管理規約、使用細則
- 総会および理事会の議事録
- 収支報告書、会計帳簿
- 組合員名簿
これらの書類は、マンションの運営状況を示す重要な証拠であり、不動産売買の際にも買主から閲覧を求められることがあります。
【トラブル別】理事長の対応マニュアルと法的措置

自主管理マンションで避けて通れないのが、住民間のトラブルです。理事長としてどこまで介入し、どのような対応を取るべきか、代表的なケースごとに解説します。
Case1: 管理費の滞納が発生した場合の対応フロー
管理費の滞納は、組合の財政を揺るがす重大な問題です。感情的にならず、法的手続きに沿って淡々と対応することが重要です。
- 初期対応(1〜2ヶ月滞納):まずは電話や書面で支払いを丁寧に催促します。単なる支払い忘れの可能性もあります。
- 督促状(書面)の送付:それでも支払いがない場合、支払期限を明記した督促状を送付します。理事会で状況を報告し、議事録に残しておきましょう。
- 内容証明郵便による最終勧告:支払いに応じない場合は、「法的措置を検討する」旨を記載した内容証明郵便を送付します。これは心理的なプレッシャーを与え、後の訴訟で証拠となります。
- 法的措置の検討:最終手段として、裁判所を通じた手続きを検討します。
- 支払督促:書類審査のみで簡易裁判所から督促を出してもらう手続き。
- 少額訴訟:60万円以下の金銭請求を対象とした、原則1日で審理が終わる訴訟。
- 競売請求:他の方法で解決できない悪質なケースでは、総会の特別決議(4分の3以上)を経て、滞納者の住戸を競売にかけることも法的に可能です(区分所有法 第59条)。
管理費請求権の消滅時効に注意
管理費の請求権の消滅時効は、改正民法(2020年4月1日施行)により以下のとおりです(民法第166条第1項)。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
いずれか早い方の経過により時効消滅します。実務上、管理組合が未払いを認識してから5年が経過すると、請求権を失う可能性があります。滞納の放置は厳禁です。
Case2: 居住者間のトラブル(騒音・ペット等)への介入範囲
騒音、ゴミ出し、ペット飼育などのマナー違反は、住民間の感情的な対立に発展しやすい問題です。理事長の役割は、あくまで中立的な立場でルールを再確認し、是正を求めることです。
- 事実確認:まずは双方から個別に事情を聞き、客観的な事実(いつ、どのような音か等)を把握します。
- 注意喚起:掲示板への注意文掲示や全戸へのチラシ投函など、個人を特定しない形での注意喚起から始めます。
- 是正の勧告:改善が見られない場合、理事会の決議を経て、理事長名で対象者に対し、規約や使用細則に基づき是正を勧告する書面を渡します。
- 介入の限界:理事長の勧告に法的な強制力はありません。当事者間の話し合いで解決しない場合、理事長が無理に仲裁しようとすると、かえってトラブルに巻き込まれる危険があります。度を越した迷惑行為が続く場合は、法的措置(行為の停止請求など。区分所有法 第57条)も視野に入れ、弁護士など専門家への相談が必要です。
Case3: 総会決議の不備(瑕疵)など、運営上の法的リスク
理事長の運営ミスが、後々大きなトラブルに発展することもあります。
- 招集手続きのミス:総会の開催通知を一部の組合員に送付し忘れる、議案の要領を通知に記載しないなど。
- 決議要件の誤り:本来は特別決議(4分の3以上)が必要な規約改正を、普通決議(過半数)で可決してしまったなど。
これらの不備は「決議の瑕疵」と呼ばれ、組合員から決議の無効や取消を求める訴訟を起こされる可能性があります。重要な議案を扱う際は、手続きに誤りがないか、マンション管理士などの専門家に事前に確認を依頼することも有効なリスク管理です。
「もう限界…」理事長の重すぎる負担を軽減する3つの方法

自主管理は理想的ですが、理事長の負担が限界を超える前に、外部の力を借りる選択肢を検討することが賢明です。
方法1: 外部専門家(マンション管理士・弁護士)を賢く活用する
専門知識が必要な場面では、専門家の助言が非常に役立ちます。両者の役割の違いを理解しておきましょう。
- マンション管理士:マンション管理のコンサルタントです。理事会や総会の運営支援、規約の見直し、長期修繕計画の作成助言など、運営全般の相談に乗ってくれます。法律行為の代理はできません。
- 弁護士:法律の専門家です。管理費滞納の訴訟代理、住民間トラブルの法的対応、契約書のリーガルチェックなど、法律行為が絡む場面で依頼します。
| (費用目安) | ・マンション管理士(顧問契約):月額3万円~10万円程度(マンションの規模による) ・弁護士(法律相談):30分5,000円~1万円程度 |
顧問契約を結ばずとも、必要な時だけ相談する「スポット契約」も可能です。
方法2: 一部の業務を管理会社に「一部委託」する
「会計業務だけは専門家に任せたい」「清掃や点検の手配が大変」といった場合、特定の業務だけを管理会社に委託する「一部委託」が有効です。
- 委託できる業務の例:
- 会計業務(管理費等の徴収、支払い代行、月次報告書作成)
- 清掃業務
- 設備(エレベーター、消防設備等)の保守点検手配
コストを抑えつつ、理事会の負担が特に大きい業務をアウトソースできます。
方法3: 管理会社への「全部委託」へ切り替える際の注意点
理事のなり手不足が深刻な場合や、建物が高経年化し専門的な管理が不可欠になった場合は、管理のプロである管理会社に全体を任せる「全部委託」への切り替えも重要な選択肢です。
全部委託を検討する際は、複数の管理会社から見積もり(相見積もり)を取ることが基本ですが、注意点があります。
- 見積もり依頼は2〜3社に絞る:特に戸数が少ない自主管理マンションの場合、5社も6社も見積もりを依頼すると、管理会社から敬遠される可能性があります。管理会社は、正確な見積もり作成のために、現地調査や外注先との打ち合わせなど多大な労力をかけるため、手間とコストが見合わないと判断されかねません。
- 見積もり依頼のポイント:良いパートナーを見つける秘訣は、「どこまでを委託したいのか」という仕様を明確にし、誠実な態度で依頼することです。管理会社の労力に配慮した姿勢が、結果的に良い提案を引き出します。
- 価格だけで選ばない:委託費の安さだけで選ぶと、サービスの質が低く、結局トラブルが多発する可能性があります。「事務管理費」「管理員業務費」「清掃費」などの内訳をよく比較し、担当者の対応や実績も考慮して総合的に判断しましょう。
よくある質問(FAQ)

理事長就任は断れますか?任期はどのくらい?
管理規約に理事の就任義務が定められていない限り、法的に就任を強制されることはありません。しかし、多くのマンションでは輪番制が採用されており、円滑なコミュニティ維持のためには協力が望まれます。健康上の理由など、やむを得ない事情がある場合は、理事会に相談しましょう。
任期は規約で定められますが、国土交通省の「令和3年度マンション総合調査結果」によると「1年」が52.3%、「2年」が39.9%と、1〜2年が一般的です。
理事長に報酬は支払われるのですか?
理事の活動は無報酬が原則ですが、規約で定め、総会で承認されれば役員報酬を支払うことは可能です。同調査によると、役員報酬を「支払っている」管理組合は全体の36.8%となっています。
理事のなり手不足はどうすれば解決できますか?
理事のなり手不足は、多くの管理組合が抱える深刻な問題です。同調査でも、管理組合の悩みとして「理事のなり手が不足している」が28.7%を占めています。解決策としては、以下のようなものが考えられます。
- 役員報酬を設定し、インセンティブを設ける。
- 業務の一部または全部を管理会社に委託し、理事の負担を軽減する。
- マンション管理士など外部専門家を「外部役員」として迎え入れる。
まとめ:一人で抱え込まず、法的知識と外部の力を活用しよう
自主管理マンションの理事長の役割は、決して楽なものではありません。しかし、その責任と権限には明確な法的根拠があり、業務内容にも一定の型があります。
この記事のポイント
- 法的立ち位置の理解:理事長は組合からの「受任者」であり、「善管注意義務」を負うが、誠実な業務執行をしている限り、個人責任を過度に恐れる必要はない。
- 具体的業務の把握:総会・理事会運営、会計監督、建物維持管理、書類保管が4大業務。標準管理規約が業務の指針となる。
- トラブル対応の型:滞納や住民間トラブルには、感情的にならず、法的手順や規約に沿った冷静な対応が求められる。
- 負担軽減策の活用:全ての業務を一人で背負う必要はない。マンション管理士や弁護士、一部委託サービスなどを積極的に活用することが、持続可能な組合運営の鍵となる。
理事長の仕事は、マンションという大切な資産と、そこに住む人々の快適な暮らしを守る、非常にやりがいのある役割です。この記事で得た知識を基に、他の理事や組合員と協力し、そして時には外部の力も借りながら、円滑な管理組合運営を実現してください。
免責事項
本記事は、マンション管理に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の個別事案に対する法的助言を行うものではありません。理事長としての具体的な判断や対応については、必ず自マンションの管理規約を確認の上、弁護士・マンション管理士等の専門家にご相談ください。また、法令は改正される可能性があるため、国土交通省等の公式情報で最新の内容をご確認ください(本記事は2025年10月16日時点の情報に基づきます)。
参考資料
- e-Gov法令検索. 「民法」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- e-Gov法令検索. 「建物の区分所有等に関する法律」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
- 国土交通省. 「マンション標準管理規約(単棟型)」. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001738206.pdf
- 国土交通省. 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720466.pdf
- 国土交通省. 「令和3年度マンション総合調査結果」. https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001750419.pdf
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。