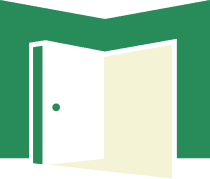2025.05.24
- column
マンションの騒音トラブル 騒音の種類と対策|解決の為にはどうする?
皆様、こんにちは!MIJの橋立です。
今回はマンションのトラブルで大きな割合を占める騒音トラブルについてお話させていただきます。
【目次】
~騒音の種類と対策~
・固体音と 空気音
・固体音の具体例と対策
・空気音の具体例と対策
・固体音+空気音の具体例と対策
~解決の為にはどうする?~
・騒音の発生源の特定
・コンクリートは音を伝えやすい
・マンションの構造による音の増幅
・騒音問題の解決はなぜ難しい?
・管理組合や管理会社の立場
・管理組合や管理会社は何ができるの?
・当事者の話し合いや管理組合の注意喚起でも解決しない場合
・何故立証が難しいのか
・訴訟以外の解決策は?
・まとめ
~騒音の種類と対策~
騒音は、聞く人にとって不快に感じる音で、主に「空気音」と「固体音」の2種類に分類されます。それぞれの音の特性を理解し、適切な対策を講じることが、快適な生活空間を作るためには重要です。
1.固体音
固体音は、建物の床、壁、天井などの構造部分が振動することによって発生する音です。例えば、足音や物が落ちた音、給排水音などが固体音に該当します。この音は、建物の構造に大きく影響され、振動を吸収する工夫が必要です。マンションでは、音を伝えにくくするための防振対策が有効です。
2. 空気音
空気音は、空気を通じて伝わる音です。例えば、近隣での会話や交通音、工事の音などがこれに当たります。マンションでは、隣の部屋から聞こえる話し声やペットの鳴き声も空気音の一種です。空気音の対策には、空気の流れを遮断することがポイントです。音を吸収する素材を使うことで、音の伝播を防ぎます。
マンションにおいてトラブルになりやすいのは固体音の方です。また、音の伝わり方によって、空気音と固体音の組み合わせ(固体音+空気音)の騒音も発生します。では具体例と対策について見ていきましょう。
固体音の具体例と対策
-
足音
足音は特に下の階に響きやすく、特にお子さんが走り回ったりジャンプしたりすることで騒音が発生します。対策としては下記が考えられます。-
足音を立てないように気を付ける
-
床に防音マットやカーペットを敷いて振動を抑える
-
家具の配置を工夫して、走り回りやジャンプをしにくい環境を作る
-
-
ドアの開閉音
ドアの開閉音は、特に深夜に帰宅した際や急いでいる時に大きく響くことがあります。対策としては下記が考えられます。-
ドアの開閉は静かに心掛ける
-
ドアクローザーを設置して、閉まるスピードを調整する
-
すき間テープを貼ることで衝撃を和らげ、開閉音を軽減する
-
-
洗濯機の音
洗濯機はその振動と稼働音が下の階に響きやすいです。対策としては下記が考えられます。-
洗濯機を水平に設置して振動を最小限に抑える
-
洗濯機用防振マットを使用して床への振動を軽減する
-
洗濯機を使用する時間帯に配慮し、一般的には朝7時〜夜21時の時間帯に使用する(マンションの規約に従う)
-
これらの対策を実施することで、固体音の騒音を効果的に軽減し、快適な生活空間を維持することができます。続いては空気音の具体例と対策です。
空気音の具体例と対策
-
目覚まし時計のアラーム
目覚まし時計のアラームは、意外と近隣の迷惑になることがあります。特に夜勤の人や、アラームを長時間鳴らしっぱなしにしている人は注意が必要です。-
アラームを鳴らす部屋の窓は必ず閉めること。
-
アラーム音を小さく設定し、鳴ったら速やかに消すようにする。
-
光や振動、電気ショックなどの目覚ましツールを活用して音を抑える。
-
-
人の声
人の声は最も身近で、生活音の中でよく耳にする騒音です。特に赤ちゃんの泣き声、子どもの騒ぐ声、大人の大声などが含まれます。-
子どもの声:分別がつく年齢の子どもには、騒がないようしっかり言って聞かせる。
-
大人の声:お酒や友人との会話で声が大きくなりがちなので、自覚して自制することが大切。
-
赤ちゃんの声:正直、ご両親含めてどうしようもないのが赤ちゃんの声です。特に夜泣きが酷い赤ちゃんの場合には、事前に近隣の方々へ「赤ちゃんの夜泣きでご迷惑をおかけします」等と謝罪・挨拶しているだけでトラブルになりづらかったりもします。(人は想像以上に全く知らない人の声等を不快に感じてしまいます。)
-
これらの対策を実施することで、固体音の騒音を効果的に軽減し、快適な生活空間を維持することができます。続いては固体音+空気音の具体例と対策です。
固体音+空気音の具体例と対策
1.楽器
楽器の音は空気音として伝わり、床や壁から振動して固体音にもなります。演奏中の騒音に配慮が必要です。
-
楽器は外壁側ではなく、内部の部屋に設置する
-
壁に接触しないようにし、振動が伝わらないようにする
-
床にカーペットを敷き、楽器の足部分に防振マットを使う
-
演奏する時間帯に配慮し、遅くとも夜20時までに終える
-
演奏中は窓やドアを閉め、防音カーテンを使う
-
防音室や防音ボックスを設置し、リフォームを検討する
-
近隣住民にあいさつし、事前に演奏する旨を伝える
2. 掃除機
掃除機は空気音と固体音の両方を引き起こし、特に時間帯によっては騒音として不快感を与えることがあります。
-
掃除機を使用する時間帯に注意する(一般的には朝8時から夜20時まで)
-
早朝や深夜の場合はフローリングワイパーなど騒音が出ない掃除グッズを使用する
-
自動ロボット掃除機を使う場合は、静音機能があるものを選び、衝撃を抑える機能を活用する
3. テレビ・AV機器
テレビやAV機器の音は空気音として伝わり、機器が壁に接触していると振動が固体音として伝わり、騒音になることがあります。
-
テレビやオーディオを壁からできるだけ離して設置する
-
壁に市販の遮音シートを貼る
-
深夜や早朝は音を出さないようにし、窓を開けっぱなしにしない
4. ペット
ペットの鳴き声は空気音、走り回る足音は固体音として騒音となることがあります。特に夜間や長時間のムダ吠えなどが問題になる場合があります。
-
ペットのしつけを見直し、ストレスケアを行う
-
しつけ教室などで専門家のサポートを受ける
-
鳴き声や足音が気になる場合は、環境を整えてペットが落ち着くよう配慮する
マンションの騒音トラブル ~解決の為にはどうする?~
よく管理会社や管理組合に騒音の相談をしたが何もしてもらえない等という声を聴くことがあります。ではなぜそういったことが起こるのでしょうか。
まず騒音の発生源の特定が難しい。
マンションでの騒音トラブルが厄介な理由の一つは、騒音の発生源が特定しづらいことです。例えば、上の階だと思ったら、斜め上の階の音だった。隣の部屋だと思ったら、共用部分にある設備の音だったなどは本当によくあります。こんなふうに、騒音問題には複雑な事情が絡むことが少なくありません。簡単には解決できない難しい問題です。
コンクリートは音を伝えやすい
一般的にマンションの壁や床はコンクリートで作られていますが、コンクリートは実は音を伝えるのが非常に得意です。コンクリートは空気の15倍も音が伝わりやすく、足音や洗濯機の振動など、壁や床に直接伝わる騒音は、真下の部屋だけでなく、下の階やその隣の部屋にも響き渡ります。
マンションの構造による音の増幅
また、マンションの構造にも原因があります。マンションの床の下(天井の上)には配管のための空間があり、コンクリートとコンクリートの間に空気の層が存在しています。この空気層が、音を増幅させるため、音が伝わりやすく、発生源を特定しにくくしています。
このように、コンクリートとマンションの構造が、騒音が発生源がどこなのかを分かりにくくしている要因となっています。
騒音問題の解決はなぜ難しい?
騒音問題は非常に複雑で解決が難しいことが多いです。まず、音の感じ方は人それぞれ異なるため、誰が正しいかを明確にすることが難しいです。例えば、騒音を訴える人が実際には音に過敏で、他の人には聞こえない音まで気になってしまうことがあります。そうなると、加害者とされる側からは「そんな音は出していない」と反論されることもあります。
管理組合や管理会社の立場
マンションの管理組合は、区分所有法で共用部分の管理をするもの定められており、基本的にその範囲でしか対応できないため、騒音問題などの専有部分に関するトラブルには原則として関与できません。管理組合の主な役割は共用部分の管理に限られており、個々の住戸で発生した問題は当事者同士で解決するよう促すことになります。
上記は、管理組合から共用部分の管理について委託を受けている一般的な管理会社も同様の立場となります。
管理組合や管理会社は何ができるの?
管理会社は入居者の悩みを受け止める身近な相談窓口ですが、対応できる範囲には限りがあります。そのため、現場のスタッフも対応に苦労することがあります。管理組合や管理会社は中立的な立場でお部屋に立ち入ることもできないため、音が出たり出なかったりするタイミングを合わせて調査するのは非常に難しいです。実際の対応として張り紙などで注意喚起を繰り返すことことや話し合いの場を設けることはできますが、基本的には当事者同士で解決してもらうことが求められます。そのため、根本的な解決には至らないケースが多いのが現状です。ただし、複数の住戸から同じ部屋に対して苦情が寄せられている場合は、状況が異なります。この場合、個別の問題を超えて共同の利益に関わる問題と見なされるため、管理組合が介入することが可能となる場合もあります。
実際に騒音に悩んだら
騒音問題が深刻な場合、まずは冷静に状況を把握することが重要です。感情的になると解決が難しくなります。できる限り騒音の記録を取り、日時や音の種類、継続時間などを詳細に記録しましょう。スマートフォンのアプリを使って騒音レベルを測定することも効果的です。
こうして実際の騒音レベルの計測を基に親しい人に相談し、客観的な判断を仰ぐのも効果的です。その後に管理組合や管理会社へ相談する等解決へ向けて動いていくのが望ましいです。
当事者の話し合いや管理組合の注意喚起でも解決しない場合
上記の対応を試みても騒音問題が解決に至らない場合には、弁護士等へ相談をして、法的措置をとる等の対応が必要になります。しかしながら、訴訟費用の問題や、立証が難しいこともあるため一度実際に弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
何故立証が難しいのか
騒音問題において、法的な基準を一概に示すのは難しいです。音の感じ方は人それぞれで、住んでいる場所や年齢によっても異なります。また、裁判所では、特定の時間帯における騒音レベルをデシベルで制限することがありますが、騒音が基準を超えていることを証明するのは非常に難しく、立証作業が大変です。仮に勝訴した場合でも、その判決を実際に履行させることが簡単ではなく、違反の立証も困難です。
訴訟以外の解決策は?
もし話し合いで解決しない場合、調停を活用するのが有効です。調停は裁判よりも低コストで、専門家である裁判官や弁護士が間に入って問題解決に向けて話し合いを進めてくれます。手数料は数万円程度と安価であり、裁判と比べて負担が少なく済みます。調停では専門的な意見を聞くことができ、相手も公的機関が関与していることを真剣に受け止めやすくなります。
まとめ
騒音問題に直面した際には、まず冷静に記録を取り、管理組合や管理会社へ相談。管理組合や管理会社は対応出来ることが限られている為、解決が難しい場合には当事者同士で話し合い、調停などの公的機関を利用することが、問題解決への近道となります。